ワッツ
代表取締役社長
FUMIO HIRAOKA
Interview
【過去】苦難と成功の30年
ワッツが創業した30年前、100円ショップはようやく常設店舗が増え始めたものの、まだまだ催事のイメージが強かったように思います。それが今では、完全な小売りの一業態として認知されるようになったのですから、まさに隔世の感がありますね。
ワッツが100円ショップ事業を始めたきっかけは、創業者である故・平岡亮三氏とパートナーの近石弘氏が、前職で100円ショップの催事にすでに取り組んでおり、その事業が小規模ながらも成長している様子を見ていたことにあります。また、100円ショップは、大きな資金がなくても始められるという点も、事業開始の大きな理由の一つでした。
創業当時にはハーレーダビッドソンの自転車や羽毛布団など、さまざまな商品を販売していましたが、それらはうまくいきませんでした。しかし、創業時の事業として100円ショップを選んだことは、結果的に創業者の平岡亮三氏にとって幸運だったのではないでしょうか。
創業当初、資金繰りの面では非常に苦労をしたようです。何しろ創業者が潤沢な資金を持っていたわけではありませんでしたから。そのような状況の中で、ワッツ創業直後の1995年3月に平岡亮三氏の前職の会社が倒産し、その会社が運営していたディスカウントショップと100円ショップ事業を引き継ぐことができたのは、平岡亮三氏の強運が発揮されたと言えるでしょう。ディスカウントショップで得られた日々の売り上げは、資金繰りの面で本当に助かったようです。
そんな資金状況から生まれたのが、ローコスト出退店とローコストオペレーションです。お金がないため、店作りに費用をかけられませんでした。事務所仕様で借りた売り場の壁に100円ショップの幕を張り、発泡スチロールの看板を付けて、什器を置いて商品を陳列し、レジを置けば店舗が完成。閉店の際にはすべてを持ち帰る。この形式は、普通のテナントではなく“常設の催事”と呼べるものでした。それが今や30周年を迎える企業となり、“本当によく30年やってきたよね”と思います。

今日を迎えるまでの中で
印象に残っていること
やはり、ワッツが上場できたことは非常に大きな出来事でした。ワッツが最初に目指した市場は、大阪証券取引所が小規模企業の上場のために作った「大阪新市場」でした。しかし、その市場がうまく機能せず、証券会社がその市場での上場を引き受けなくなってしまったのです。
そのため、ワッツは新たに店頭市場での上場を目指すことになり、ようやく上場申請までたどり着きました。しかし、ワッツが上場申請を行ったその日にマイカルが倒産し、次は“ワッツ最大の出店先であった九州の小売企業が危ない”という危機に直面し、やむを得ず申請を取り下げることになりました。この九州の小売企業の動向がワッツの上場に大きな影響を与えていたため、しばらく上場は難しいだろうと思っていました。
ところが、その九州の会社が同年12月初めに倒産したため、当時12月決算だったワッツは、運良くその年の決算の数値で上場申請をすることができました。
ただ、ワッツが上場を果たした際、創業者の平岡亮三氏は病で療養中でした。氏が元気なうちに上場を実現できなかったことは非常に残念に思います。
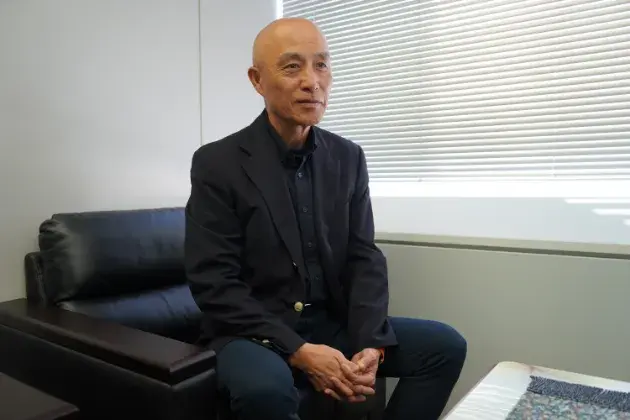
【現在】ワッツの現在地
上場申請の審査書類を作成している際、近石さんに「ワッツの創業理念は何ですか?」と伺ったことがあります。そのときの答えは「みんなで飯が食えるようになろう」というものでした。これを証券会社の審査担当者に伝えたところ、「そんなのは創業理念にはならない」「それでは上場した後、どうしたいのですか?」と言われました。
私が「もっと旨いものを食べられるようになろう、ですかね」と正直に答えると、「そんなことでは上場なんてできない」と叱られたことを覚えています。
確かに、上場を目指す企業の理念としては不適切かもしれませんが、ワッツの本質はまさにそこにあるのだと思います。
私がワッツに入社して初めて見た店舗は、近鉄八戸ノ里駅高架下の近商ストアの横にある店舗でした。売場面積は18坪ほどだったと思いますが、従業員の休憩室用に作られたプレハブ小屋の1階部分を利用した店舗でした。「これが店なのか?」というのが正直な感想でした。ただ、それは徹底したローコストを追求し、「みんなで飯が食えるようになろう」という思いが染み込んだ店だったと思います。当時、私は総務担当で、新入社員を採用する際にはその店舗を見せに行き、「これがワッツの原点だ」と紹介していたことを思い出します。
幸いなことに、100円ショップは一つのフォーマットとして広く認知され、大型モールにもテナントとして出店できるようになりました。ワッツの店舗も、当時とは比べものにならないほど広くて綺麗な店舗に成長しています。”おかげさま”で売上高も順調に伸ばすことができています。余裕があるとは言えませんが、皆さんに給与をきちんと支払うことが出来て、みんなで飯が食えている。やっぱりそれが一番大切なのだと思います。
私は100円ショップのプロでも経営のプロでもないため、事業に詳しい方々の意見をよく聞き、合理的な経営判断を行うよう努めてきました。日々、自分自身が会社にとって有益な存在であり続け、少しでも役立てる部分を見つけ、それを確実に実践できるよう心掛けています。

【未来】ワッツのこれから
企業というものは「経営者の想像をはるかに超えて、今日の姿に至っている」ということは、あまりないのではないかと思います。つまり、現在のワッツの姿も、平岡史生が想像した範囲内にあると言えます。もちろん、20数年前に私が想像していたワッツの将来像は今の姿と同じではありません。しかし、それでも大きく外れたものではなく、想像の範囲内に収まっていると感じています。
しかし、世界の状況はめまぐるしく変化し、過去の成功体験が通用しなくなっています。AIやSNSの活用やEコマースなどはまさにその領域なのだと思います。そして、その領域をうまく使いこなせないと、10年後20年後には取り残されてしまうでしょう。ただ、その領域を使いこなし、今後の将来像を描いていくのは私の役割ではないと思っています。
そうは言っても、これからの10年ほどは100円ショップがワッツの中心事業であることに変わりはないと思っています。そのため、私に残された役割は、その10年間を生き延びられるよう100円ショップをさらに強化することと、新しいリーダーとなる人材を育てることです。「育てる」というのはおこがましい表現かもしれませんね。むしろ、人材の「芽を摘まないこと」が大切だと考えています。
新しいリーダーには、100円ショップがさらに成長できる姿を描き、また、ワッツの第2・第3の中心事業を想像(創造)してもらいたいと思います。そして、100周年を迎える際にも、従業員の皆さんが「みんなで飯が食える」状況を維持できていれば、それは素晴らしいことだと思います。
でも、せっかく資本主義・自由主義の日本に生まれてきたのですから、新しいリーダーには“世界に羽ばたくワッツ”を想像してもらいたいですね。かつて「プレハブの店舗を運営していても」私に向かって「一緒にワッツを上場させよう」と言ってくれた近石さんのように、経営者には身の程知らずの夢を持ってもらいたいですね。

こぼれ話
インタビュアー:ワッツができる前年の94年にご結婚された平岡社長。ご結婚前から、一緒にワッツで働いてほしいと言われていたのですか?
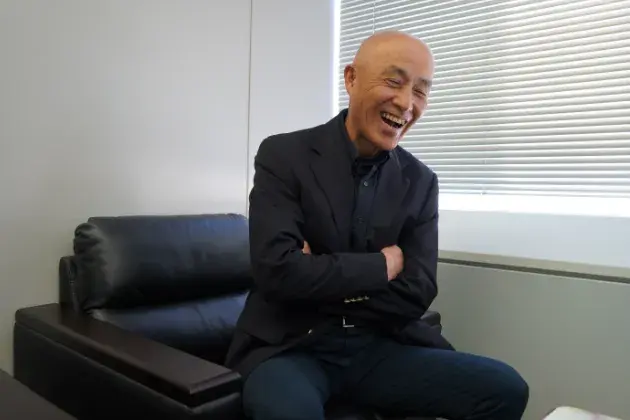
平岡社長:そんな話は全く予想していませんでした。そもそも私が結婚した時にはワッツはまだ存在していませんでしたから。奥さんが東京に嫁いでくると思い、家を建て、当時無職だった平岡亮三夫妻ともゆくゆくは同居するのだろうと思って、お二人のお部屋も用意していました。
ところが、結婚間際に「平岡姓を名乗ってくれ」と言われ、一応奥さんは東京に来たものの、3年後には結局ワッツに入社していましたね。あれよあれよと、というか、一寸先は何があるかわからないですね(笑)。
当時は教師をしていて、このまま教師の職でいいと思っていました。情熱をもって日々授業に臨んでいたし、何より楽しかったのです。それはそれで楽しい人生だったと思いますが、だいぶ違う人生を歩むことになりました。
でも、平岡亮三氏がワッツを作ろうとしたとき、周りは猛反対したのですよ。当時、亮三さんは60歳という高齢であり、その年齢で起業して成功するなんて誰も思っていませんでした。ただ、いろいろと諸般の事情があり、亮三さんとしては起業せざるを得なかったのです。その時に100円ショップを選び、周りには近石さんがいて、その後、前職の会社が倒産したこともあって、事業はすぐに拡大できました。
越智さんや福光さん、加藤さんなど、多くの人たちが前職の会社から移ってきてくれ、紆余曲折はあったものの、会社を成長させることができたのですから、平岡亮三はとても運がついている人だったのですね。そこからすると、私、平岡史生もとても運がついている人だと、つくづく思います。











